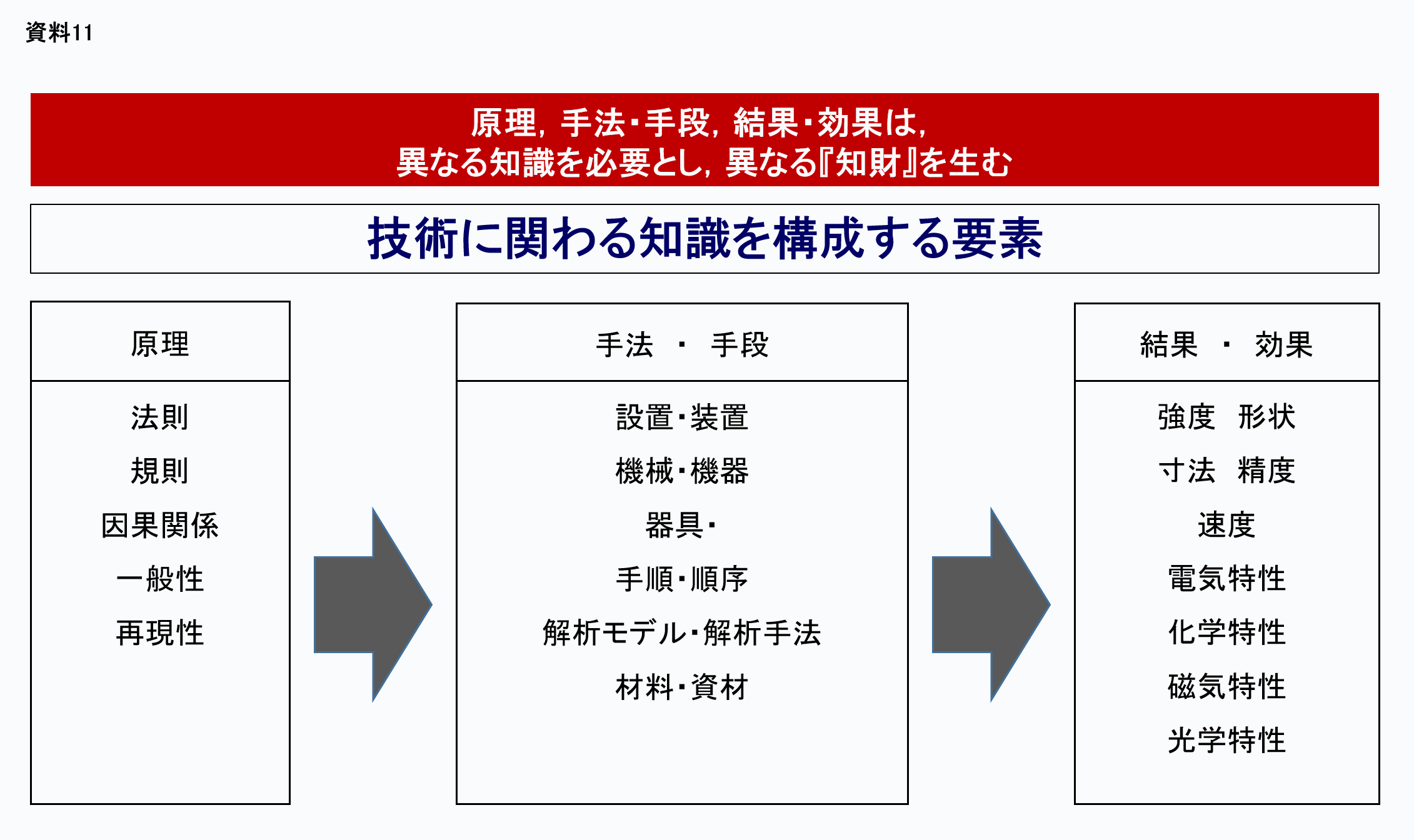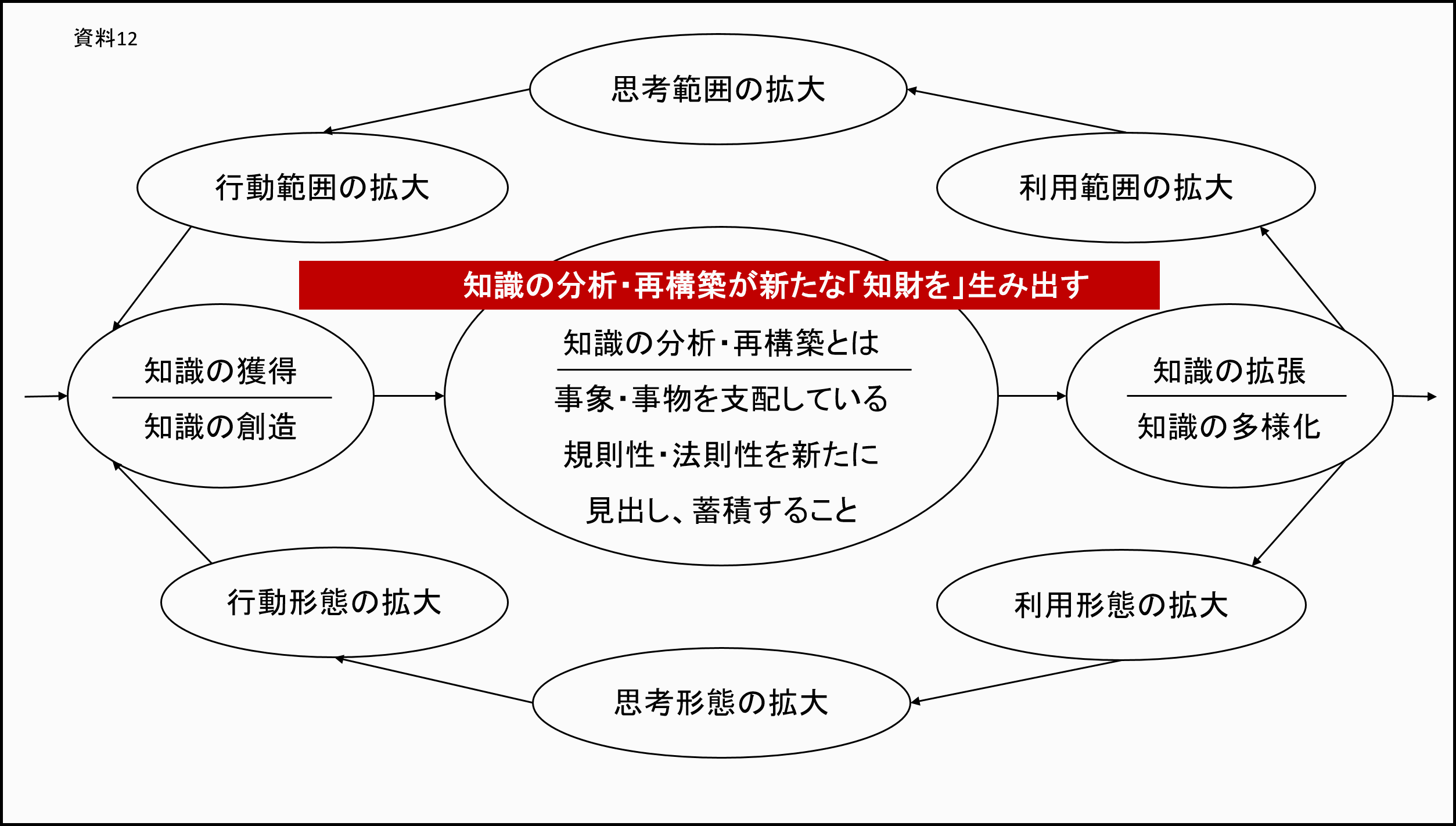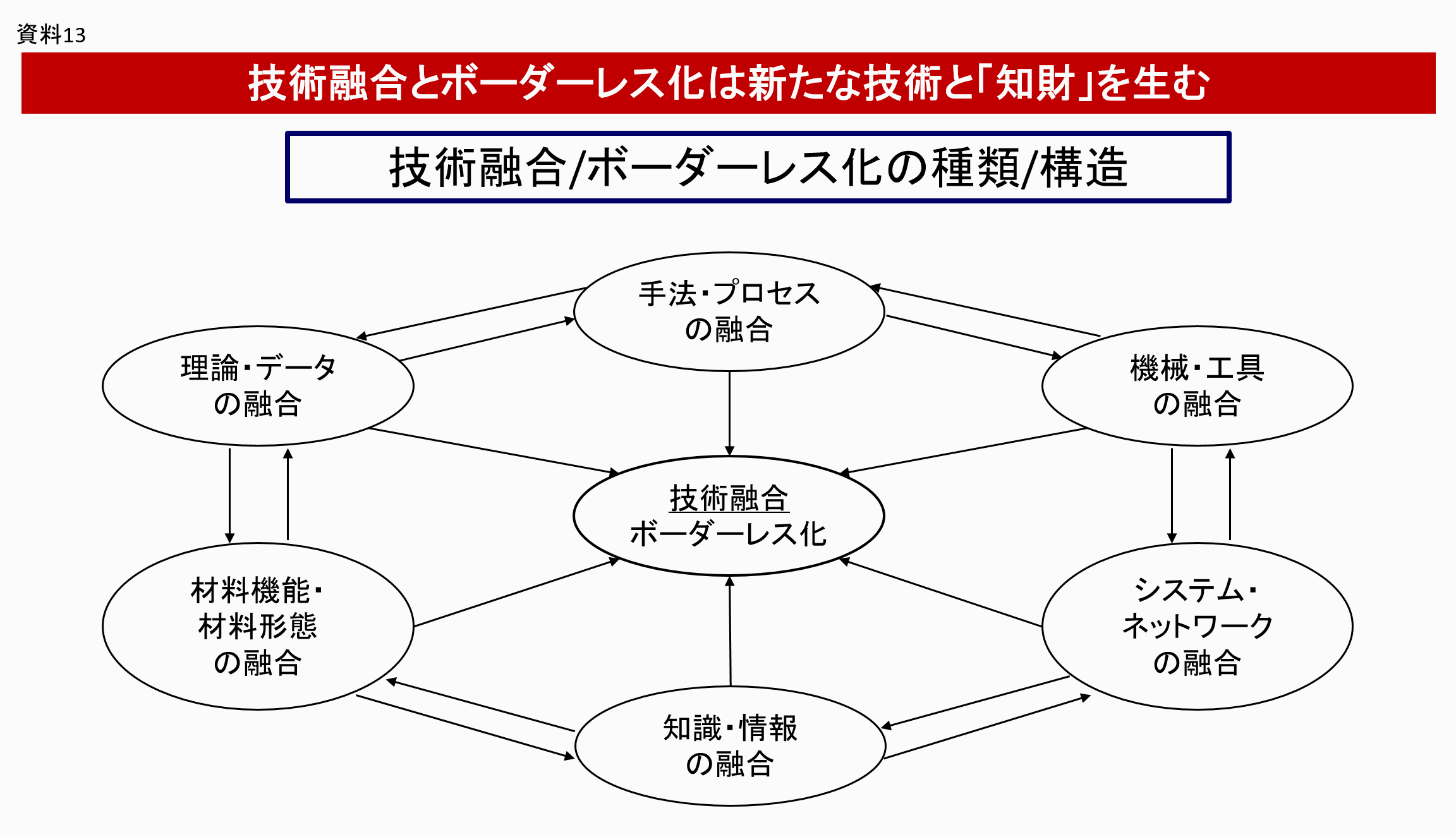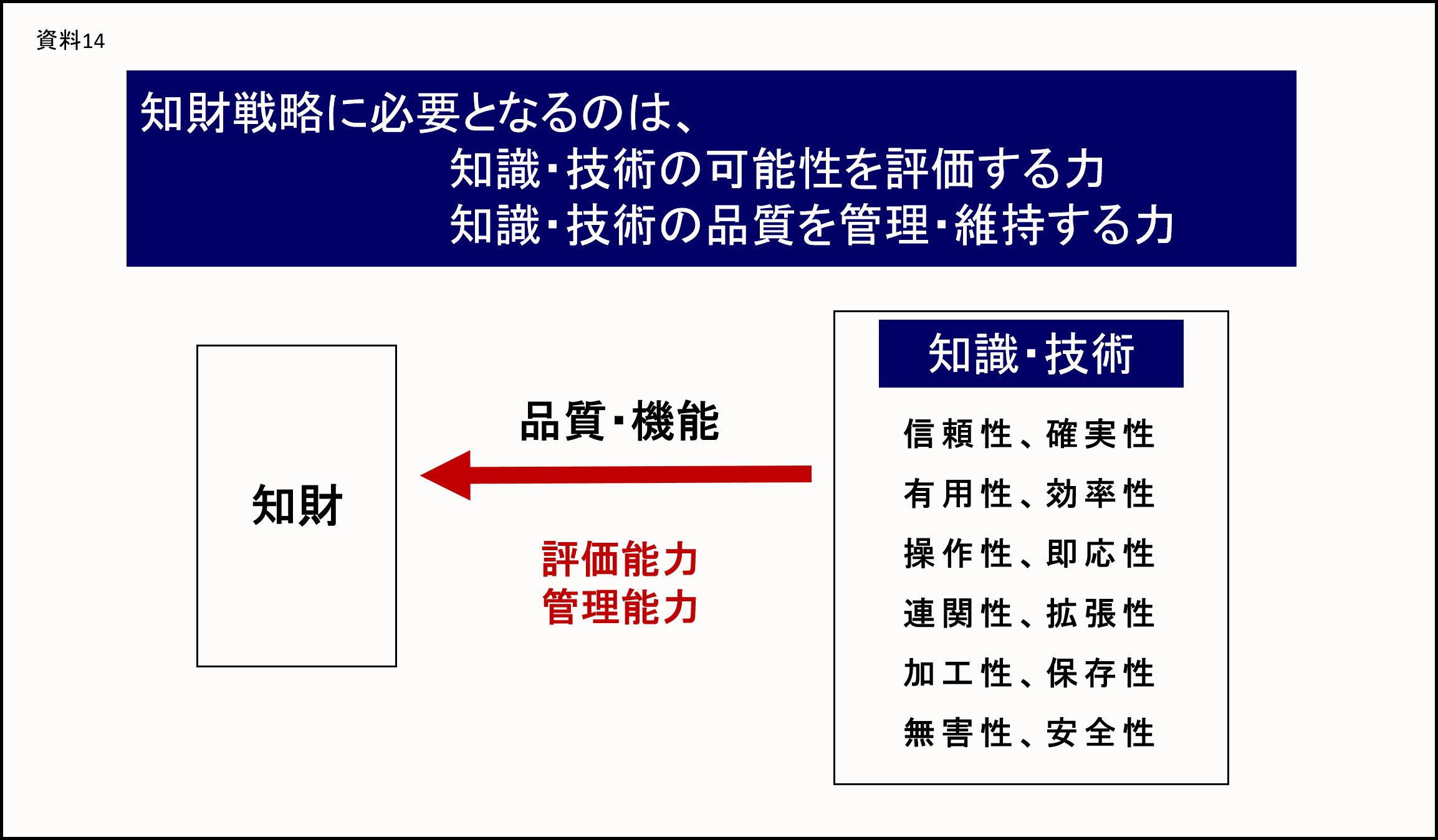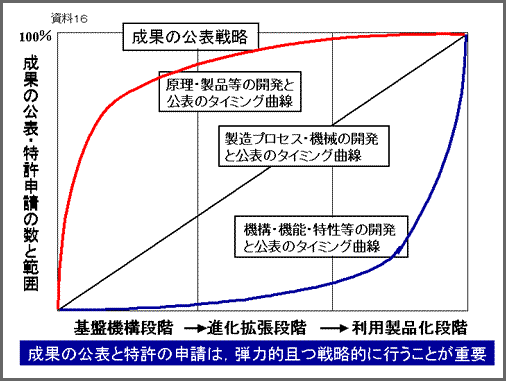技術に関わる知識は,大きく分類すると,1.原理,2.手法・手段,3.結果・効果という要素によって構成されており,各要素はそれぞれ異なる知識を必要とし,異なる「知財」を生む(資料11)。
つまり,このような知識を構成する要素をしっかり分析・整理した上で,従来の既成概念にとらわれることなく自由に技術を分析したり,技術融合・ボーダーレス化のように複数の技術を組み合わせたり,知識を再構築することなどによって,新しい「知財」が生まれてくる可能性があるということである(資料12,資料13)。
さらに,生み出した「知財」を守るという「知財戦略」においては,知識・技術の可能性を評価する力と知識・技術の品質を管理・維持する力が必要となる(資料14)。
また,特許の申請や獲得といった戦略そのものも,「知財戦略」になるということが言える。つまり,知識や知財の種類や特質によって,成果の公表と特許申請のタイミングが異なるため,両者のタイミングをどうするかということが,知識や知財を守ることができるかという結論を左右するのである。
具体的には,原理・製品の開発というのは,侵害の事実を比較的早くに発見しやすいため,その権利を初期の段階で獲得しておくのが得策であり,これに対し,製法やプロセスに関する特許については,なかなか真似されても真似された事実を発見するのが困難であるため,最後の最後の段階(利用製品化段階)に成果を公表したり,特許申請をした方が結果として特許保護につながるのである(資料15,資料16)。