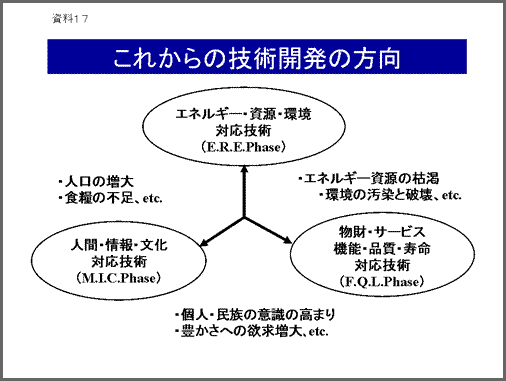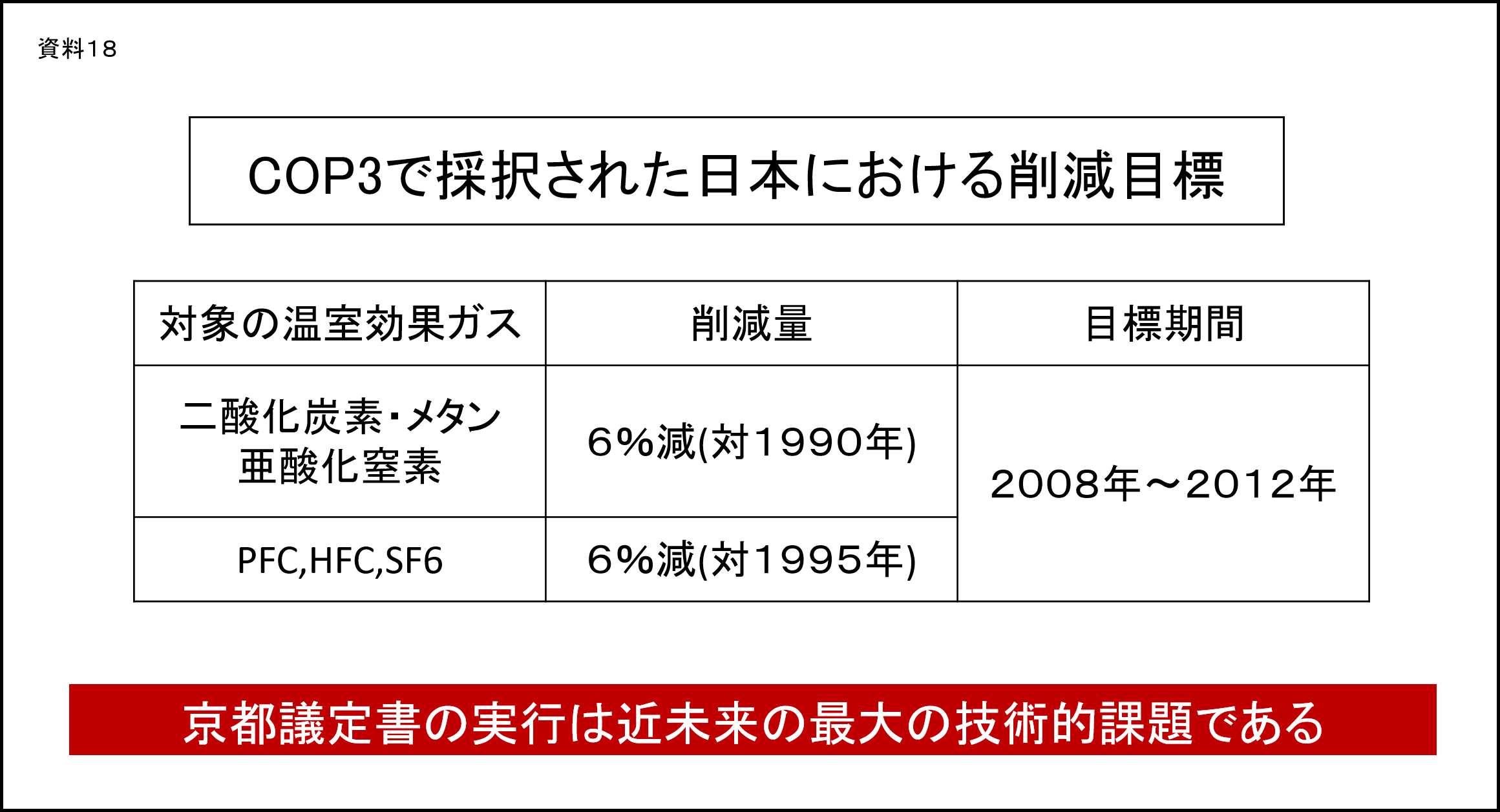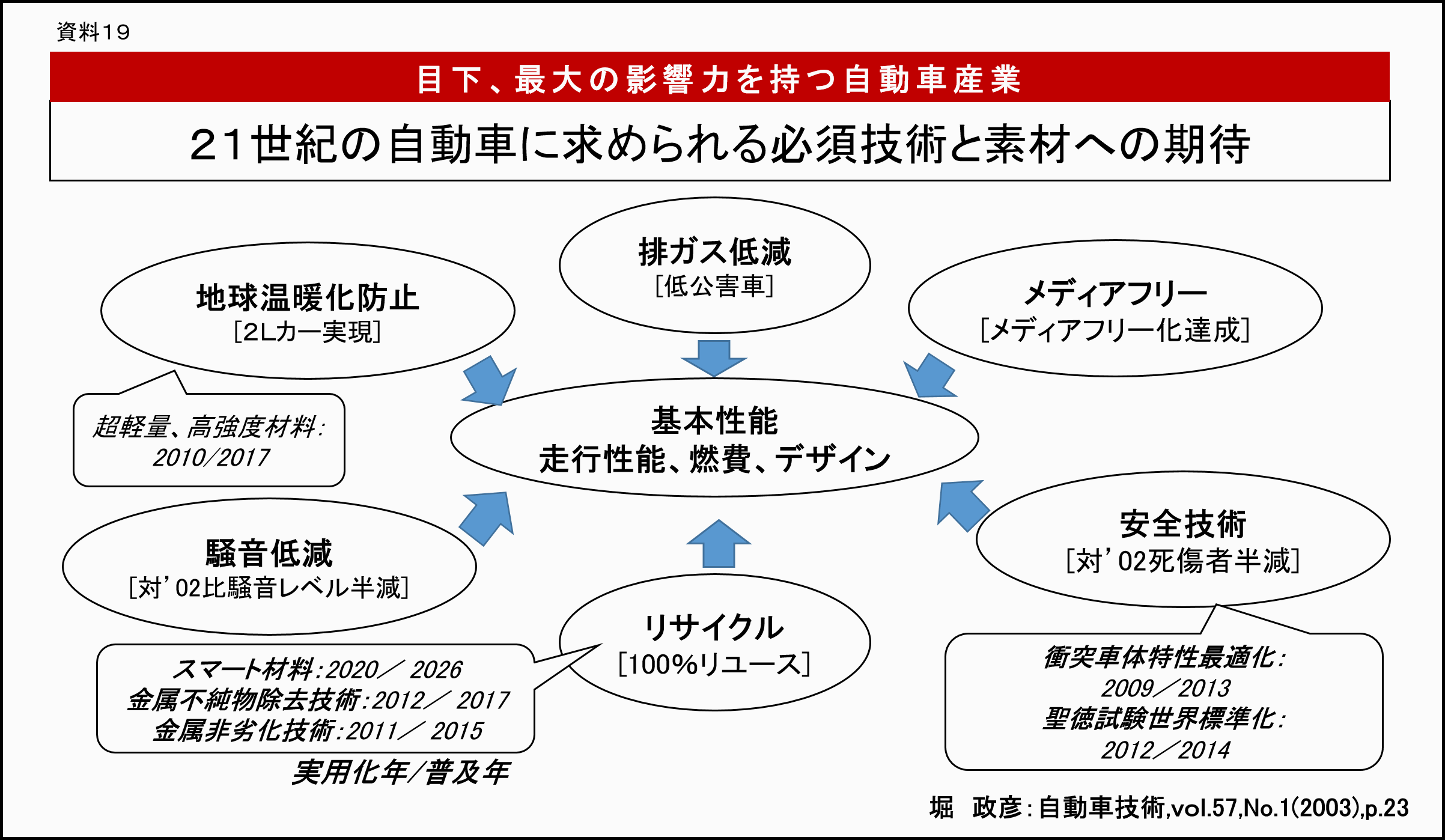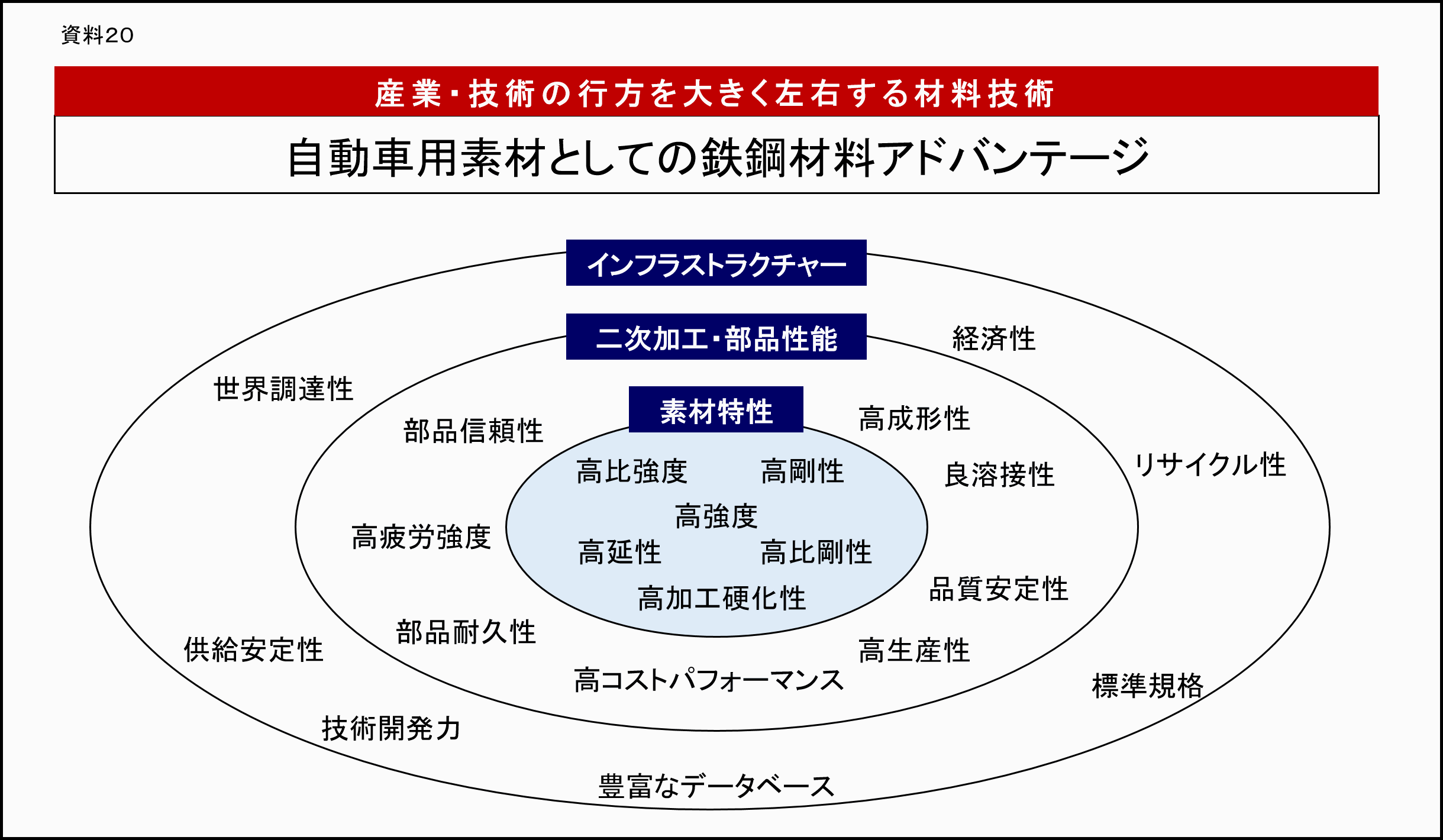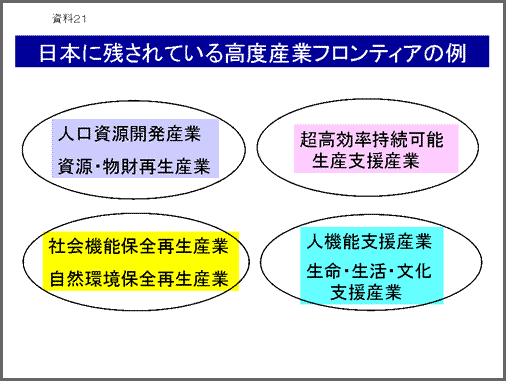これからの技術開発は,(1)エネルギー・資源・環境対応技術,(2)人間・情報・文化対応技術,(3)物財・サービス・機能・品質・寿命対応技術に向けられていくであろう(資料17)。
特に,当面の問題は,COP3で採択されたCO2 の削減であり,量的な目標値が定められていることから,その実行は日本の技術の近未来の最大の課題であると考えなければならないし,これくらいの勢いがなければ,実行は難しいであろう。そして,ここ数年間は,これに関連した新しい技術開発や,これをサポートする制度の創設などがどんどんなされていくはずである(資料18)。
今後の最大の問題は,目下,最大の影響力を持っている自動車産業に求められる,必須技術と新しい産業技術の構想・発展の根幹をなす素材に対する技術への期待である(資料19,資料20)。
さらに,その先における我が国の技術開発は,今まで積み上げてきた日本の技術を活用した人口資源の開発や,より効率の高い産業システムの製品化等の高度産業フロンティアに向かっていくものと思われる(資料21)。