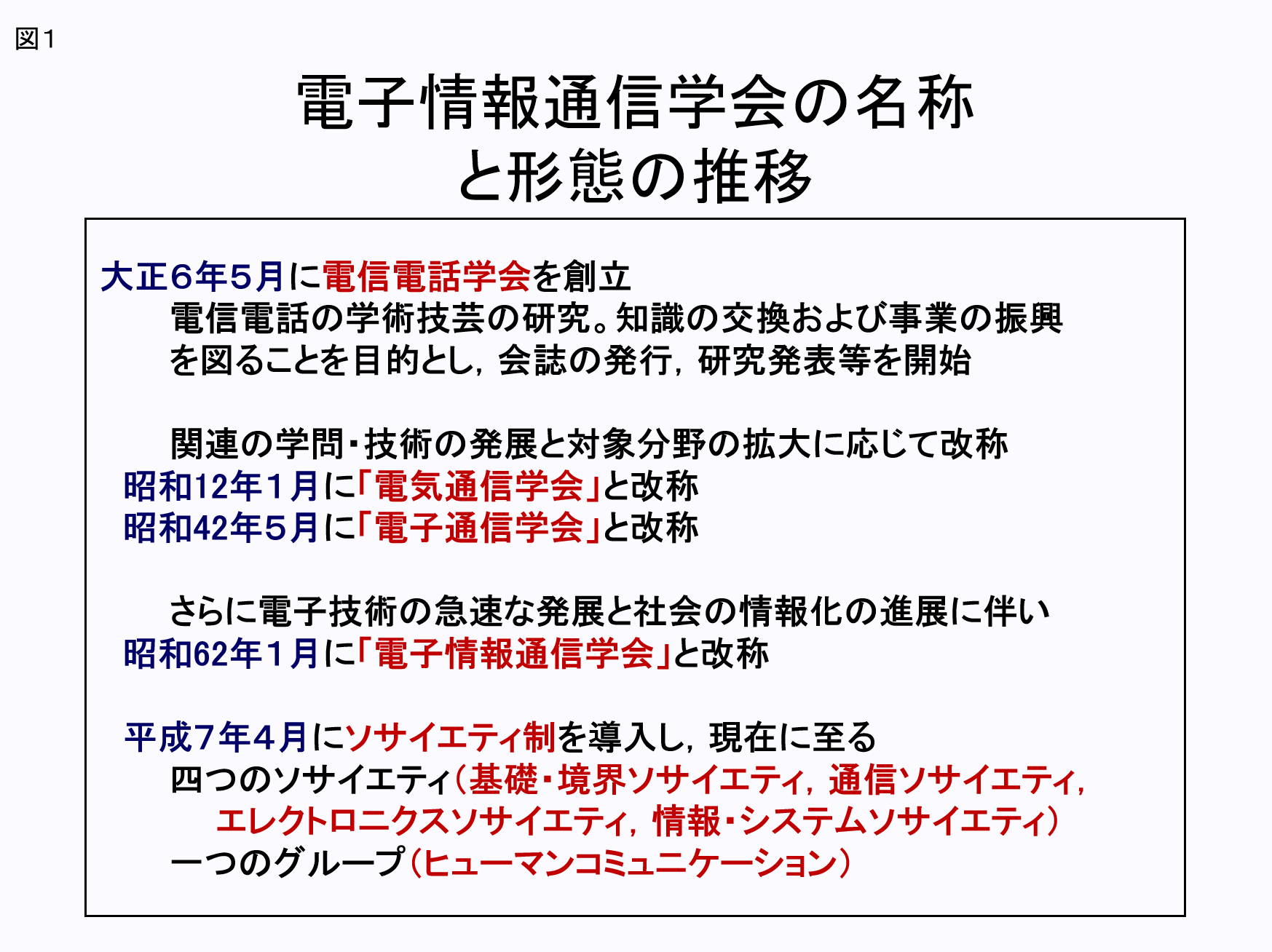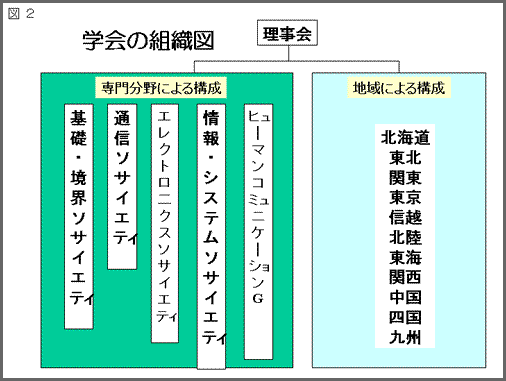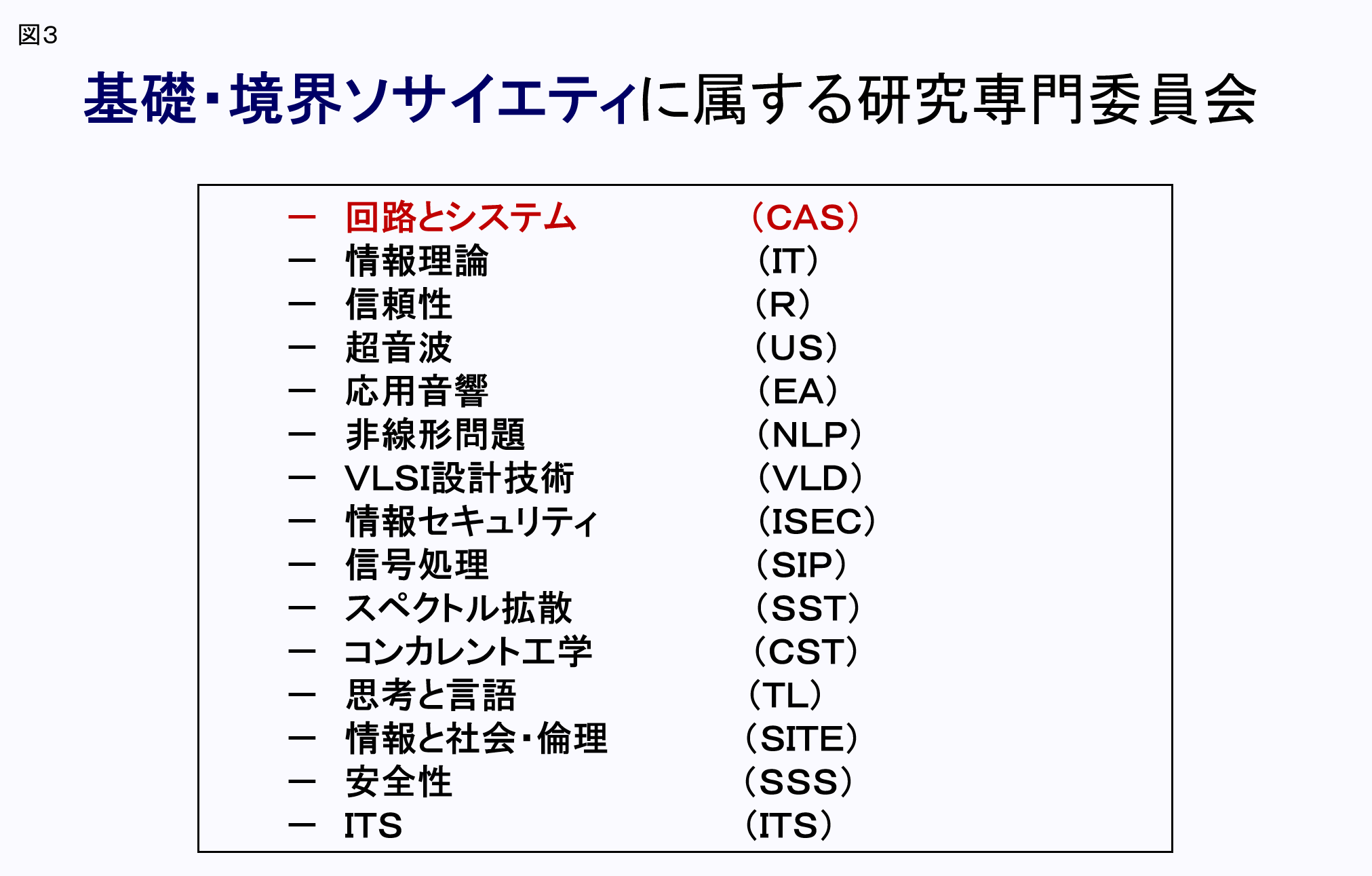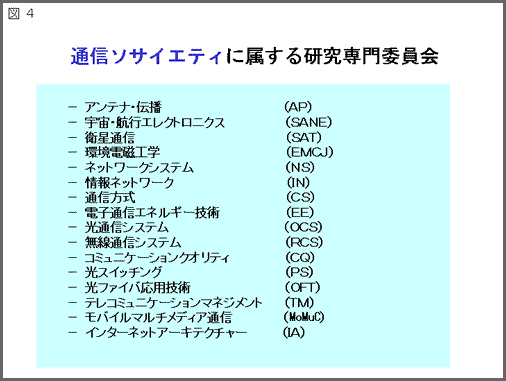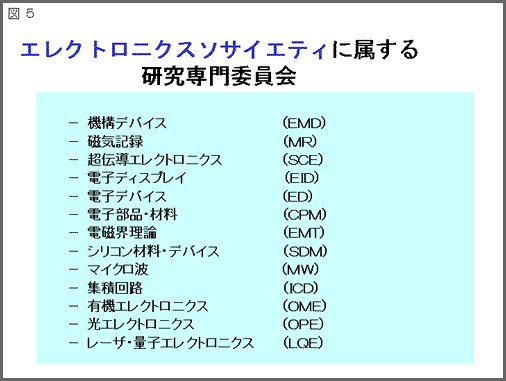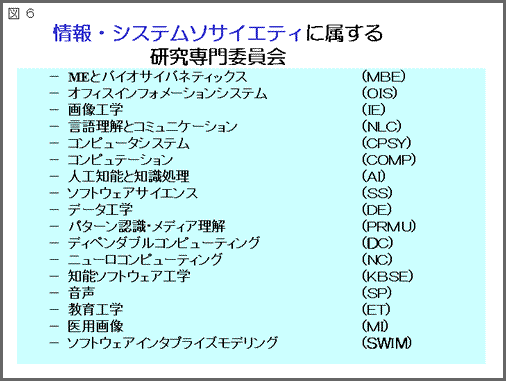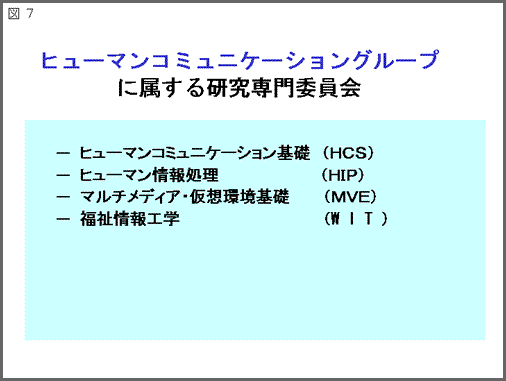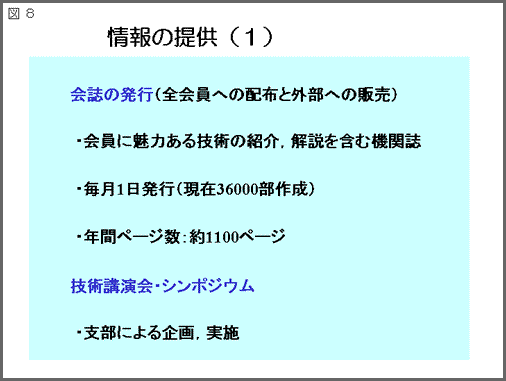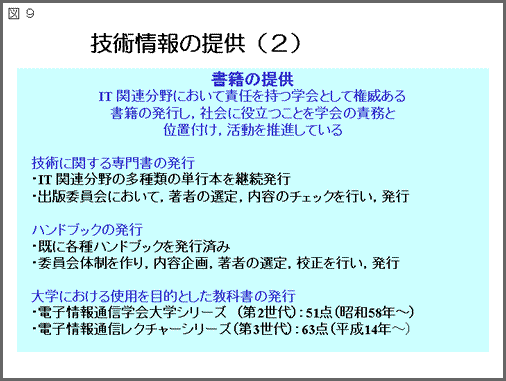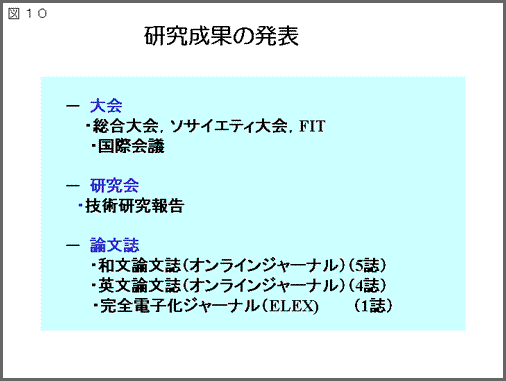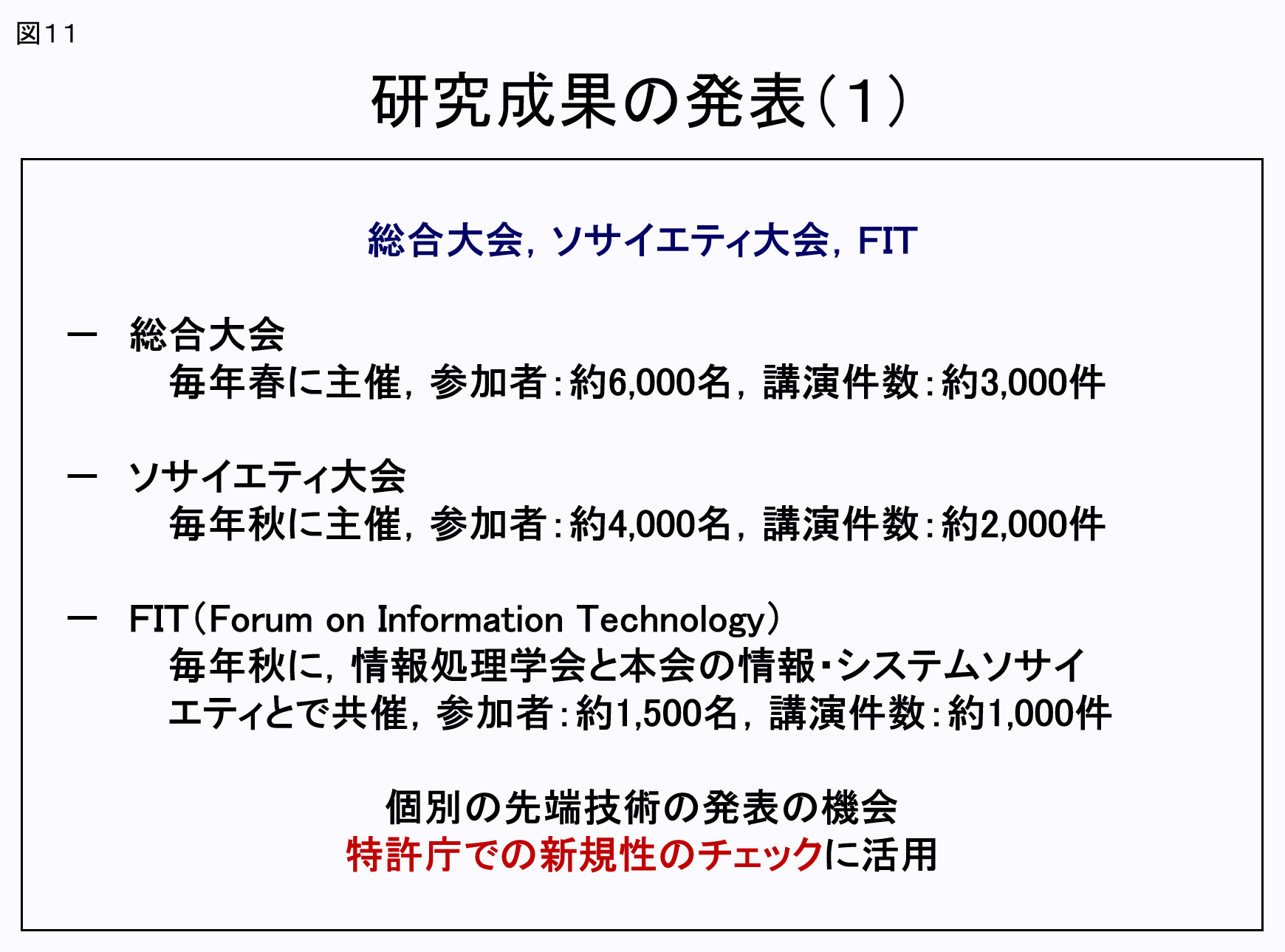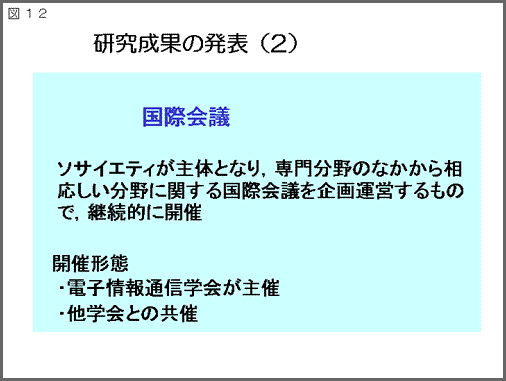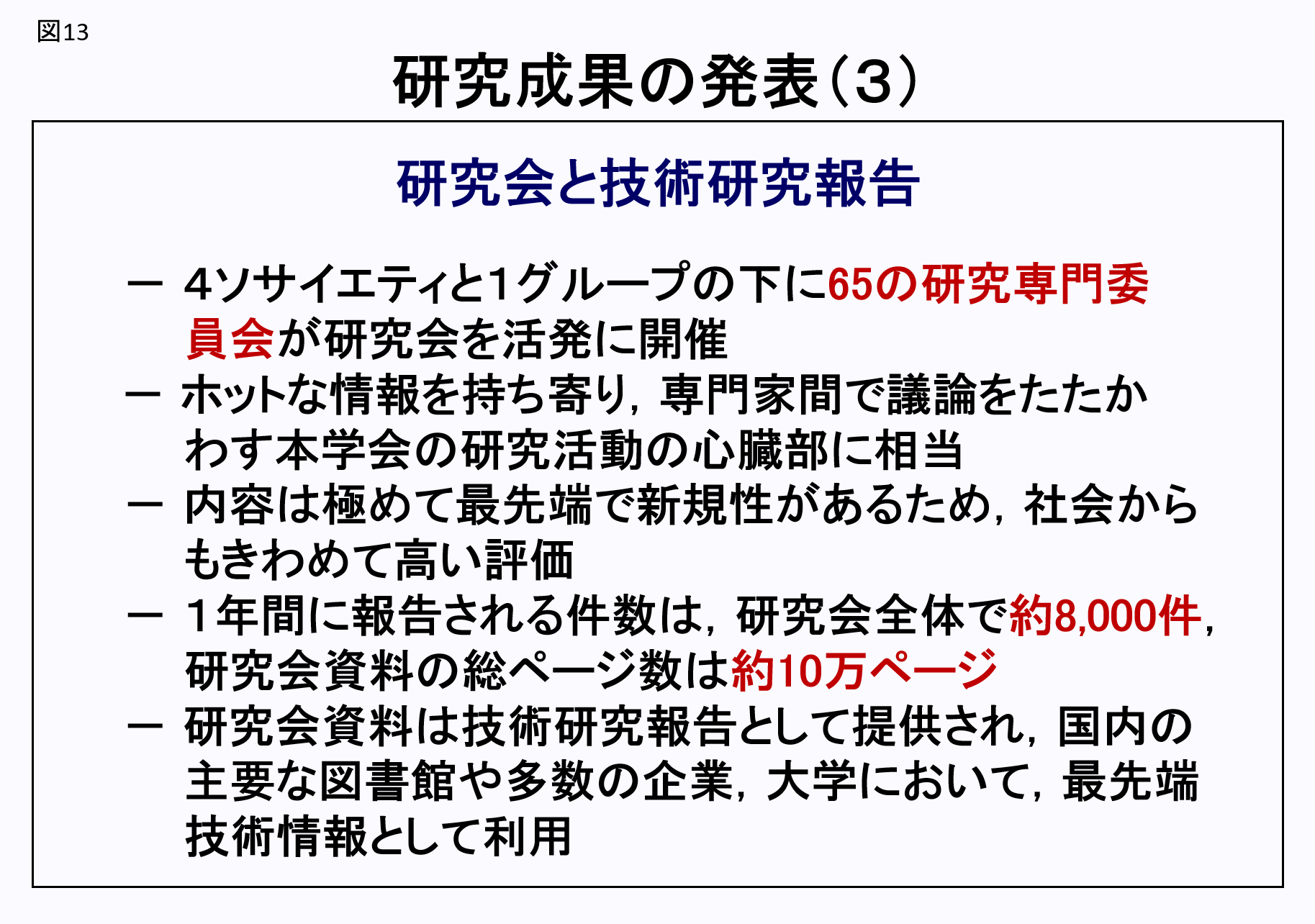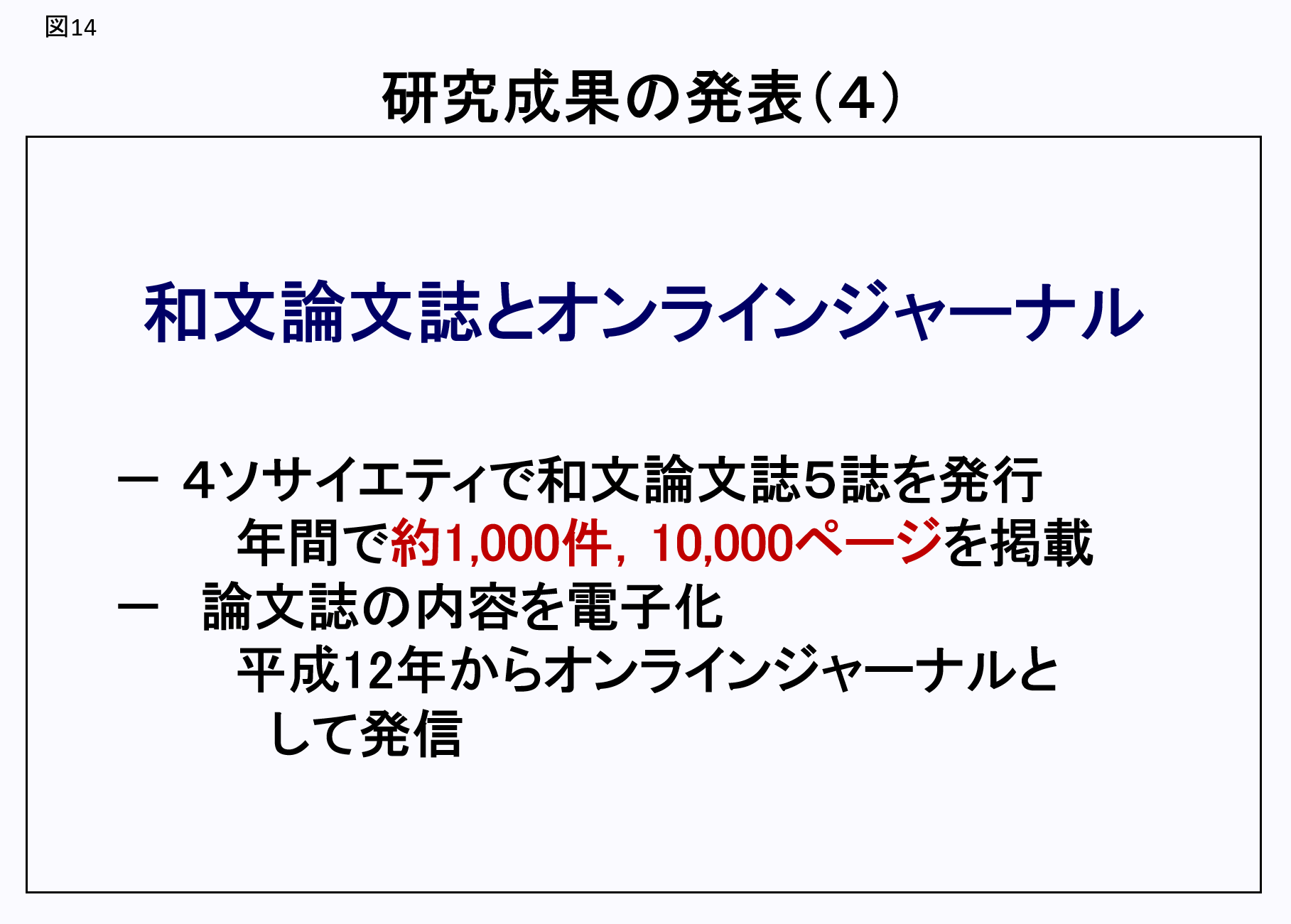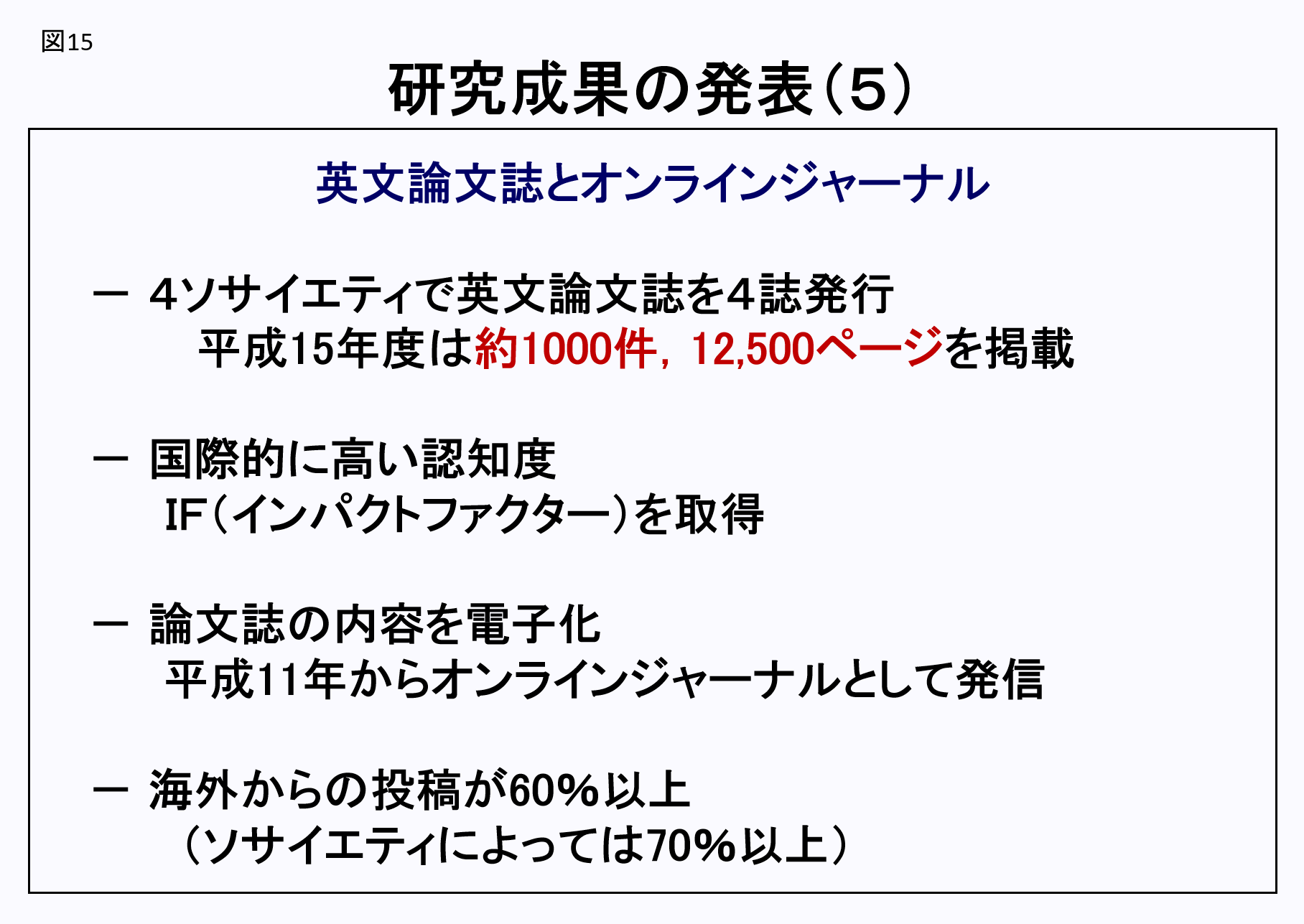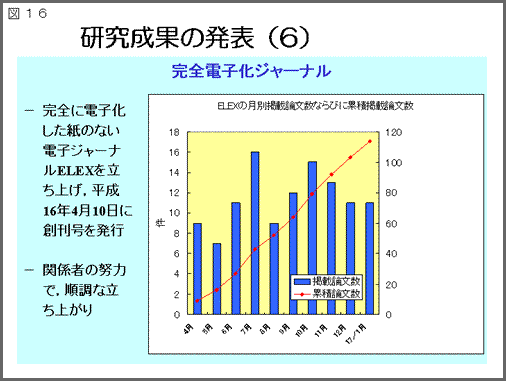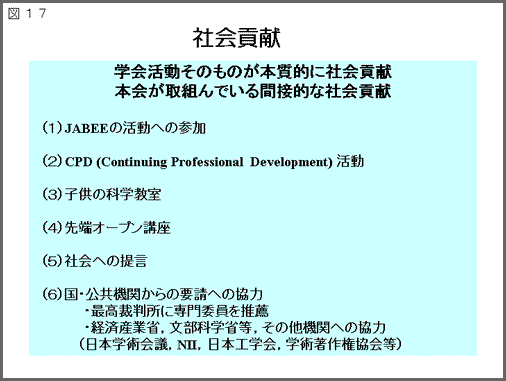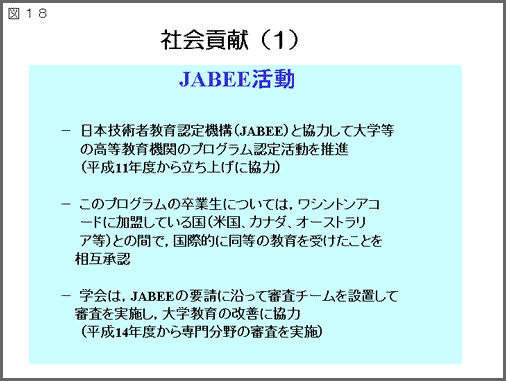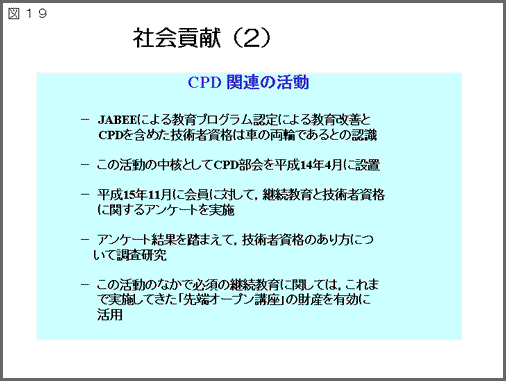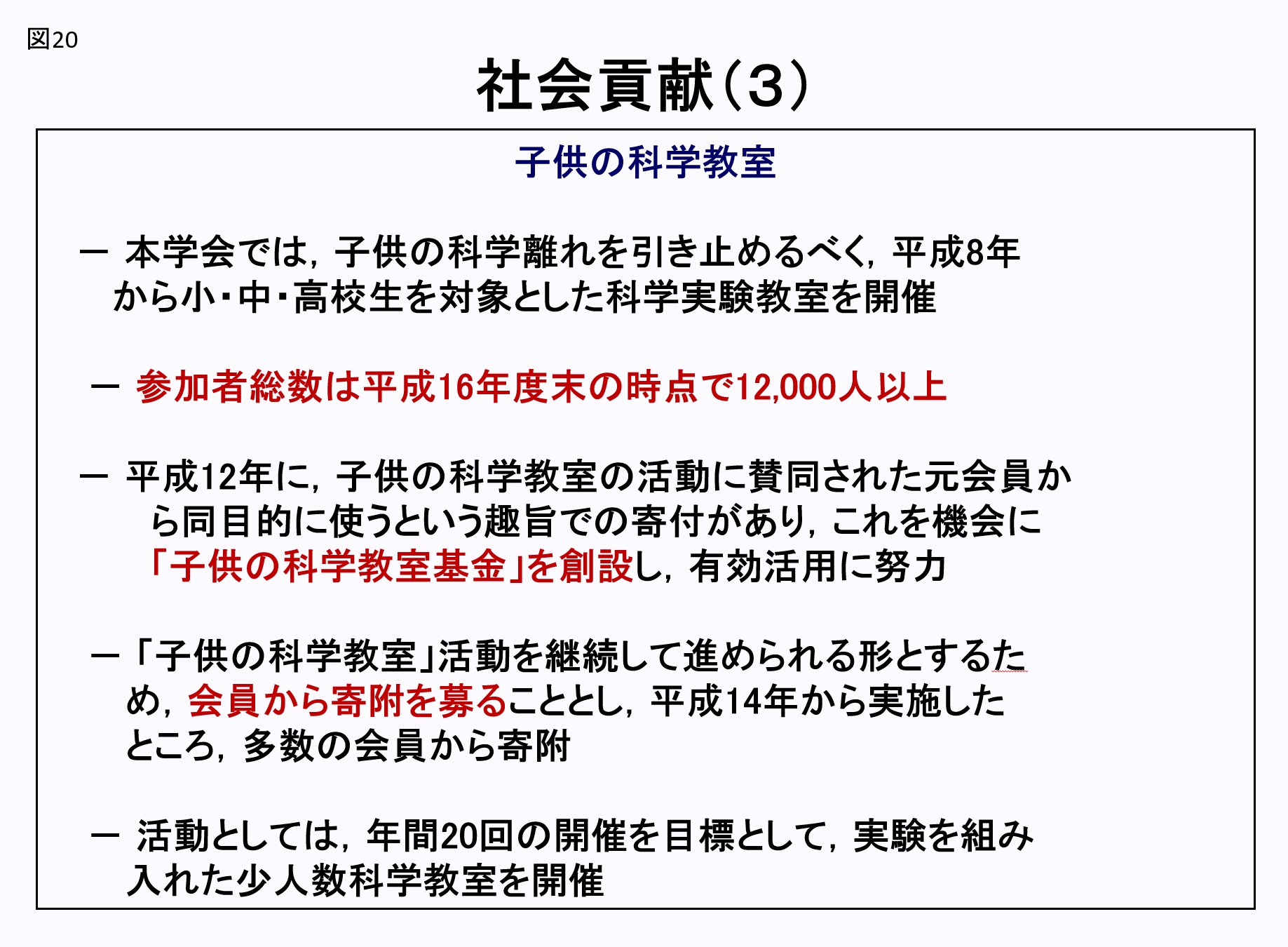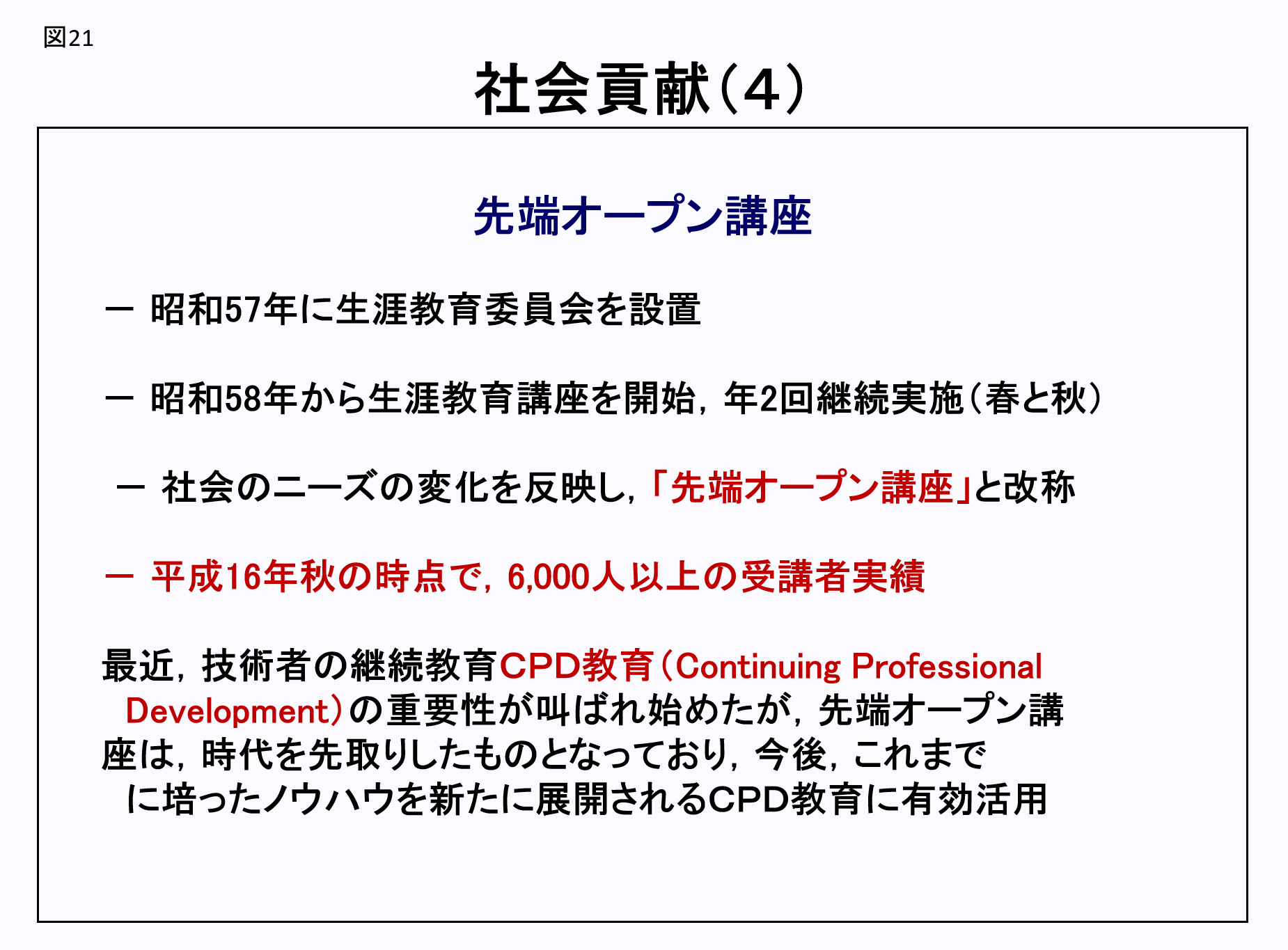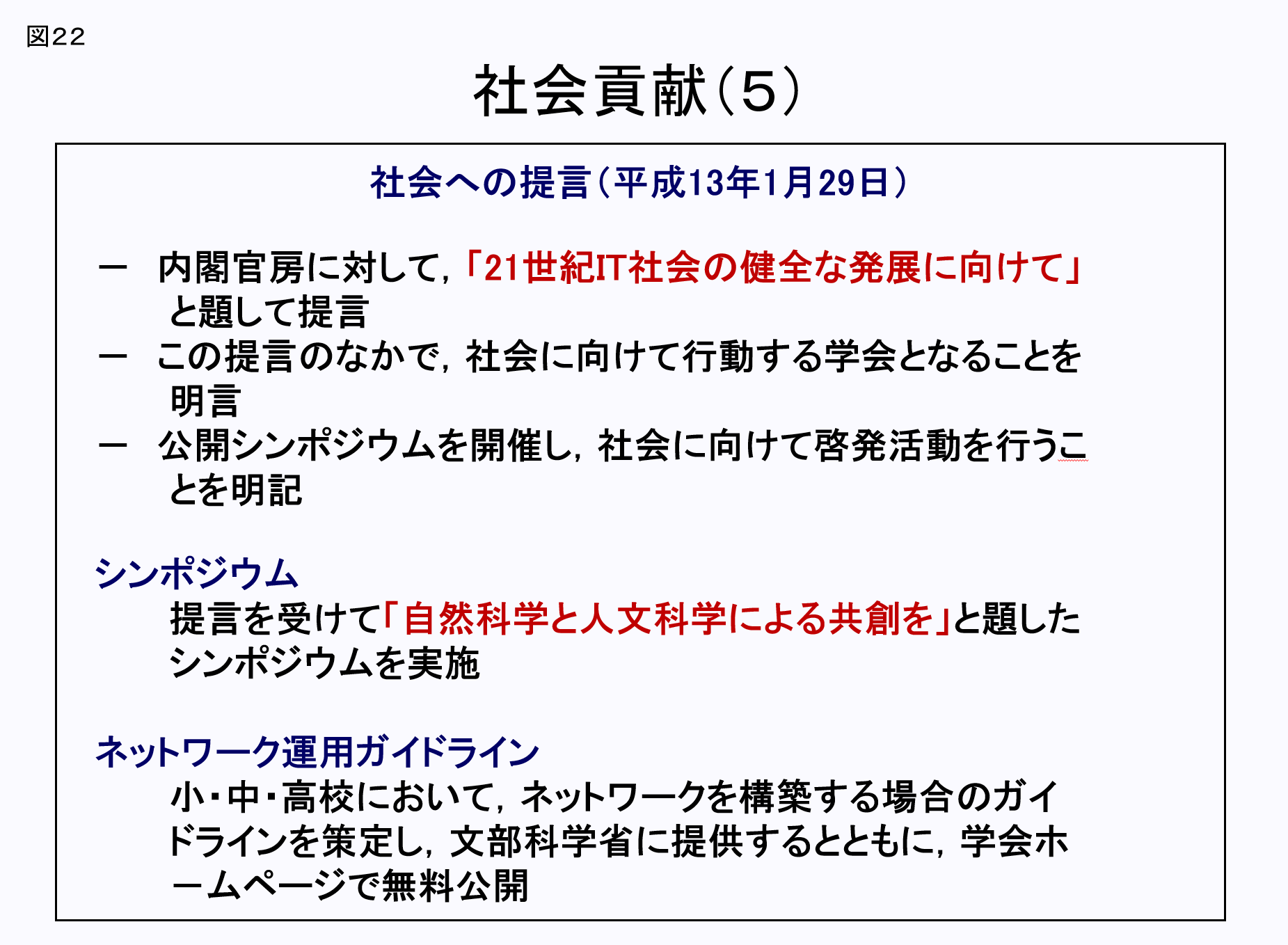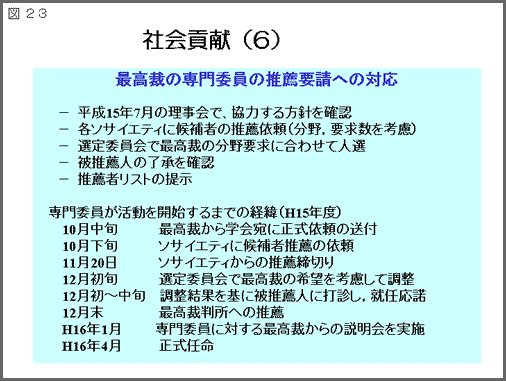電子情報通信学会は,大正6年5月,電信電話の学術技芸の研究,知識の交換及び事業の振興を図ることを目的として「電信電話学会」として創立された。その後,学問の発展による対象分野の拡大に応じて学会の名称が複数回変わっており,現在の「電子情報通信学会」という名称は昭和62年1月から使用されている。
また,関連する学問分野が広汎にわたるようになってきたこと,学問分野がより先端化していることに対応するため,平成7年4月,専門分野ごとに学会を4つのソサイエティに分けるなどの機構改革も行っている(図1,2)。
各ソサイエティの研究分野(図3,4,5,6,7)をみると,学会の運営もソサイエティごとに行われているのが分かる。
学会は,IT関連分野において責任を持つ学会として技術情報の提供,研究成果の発表を主要な活動として行っている(図8,9,10,11,12,13,14,15,16)。特に,研究成果の発表では,先端技術が発表されることから特許庁が特許審査に際し行う新規性のチェックにも利用されている。
また,学会活動は,先端技術の情報を発信するということから,それ自体が社会貢献であるが,学会ではより積極的に様々な社会貢献活動に取り組んでいる(図17,18,19,20,21,22,23)。