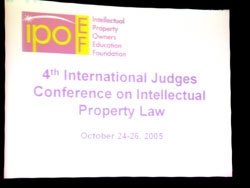平成17年10月24日から26日にかけて,アメリカ合衆国ワシントンDCにおいて,第4回知的財産法に関する国際裁判官会議(4th International Judges Conference on Intellectual Property Law)が開催され,当庁から塚原朋一判事,佐藤達文判事,東京地方裁判所より設楽隆一判事が参加しました。
この国際会議は,知的財産権者教育財団(IPO)の主催したものであり,世界約30か国から約50名の知財事件を担当している裁判官が参加し,米国からは連邦控訴審裁判所(US Court of Appeals for the Federal Circuit,以下「CAFC」)のミッシェル長官を初め,同裁判所の判事や連邦地方裁判所の判事が多数参加しました。
10月24日(月)
3日間にわたって行われた会議の第1日目の午前には各国からの裁判官のみが参加して意見交換を行うセッションが開かれました。初めに,CAFCのニューマン判事及びブライソン判事,英国王立裁判所のパンフリー判事,当庁の塚原判事がそれぞれ自国の最近の知財分野における重要な進展についてスピーチを行い,塚原判事は,主として知財高裁の設立やその概要について紹介しました。その後,出席した裁判官からも各国の知財事件の実情が紹介され,終始和やかな雰囲気の中で,率直な意見交換が行われました。
10月25日(火)
会議2日目及び3日目は,弁護士や研究者も参加しての公開セッションが開かれました。2日目の午後には,まず「各国における特許訴訟(Patent Litgation in Various Countries)」と題するセッションが開かれ,英国,ドイツ,イタリア,日本,中国,米国の裁判官や弁護士がパネリストとして参加し,仮想事例について,自国で訴訟提起することのメリットやデメリット,証拠収集手続,特許権の有効性を争うための手続などについて説明し,その後,参加者との間で意見交換が行われました。
同日午後には,引き続いて「越境的及び域外的な問題の再訪(Cross Border Issues and Extra-Territorial Issues Revisited)」と題するセッションが開かれ,特許構成要件の一部が外国で行われた場合や,外国の特許権に基づく侵害訴訟の判断,外国判決の執行などの論点について,米国及びオランダの弁護士がそれぞれ米国及びEUの裁判例を踏まえたプレゼンテーションを行い,その後,参加者も交えて議論が行われました。
10月26日(水)
会議3日目の午前には「特許要件(Patentable Suject Matter)」についてのセッションが開かれ,ドイツ,米国,日本の裁判官や弁護士がパネリストとして参加しました。ここでは,主としてバイオ特許及びソフトウェア特許の特許要件をめぐる様々な問題が取り上げられ,仮想事例に基づいて,各国の特許法を対比しつつ,議論が行われました。
同日午後には,引き続いて,「救済と損害算定の方法(Remedies and Ways of Measuring Damages)」についてのセッションが開かれ,東京地方裁判所の設楽判事,ドイツのグラビンスキー連邦地裁判事,アメリカのオマリー連邦地裁判事がパネリストとして参加しました。3名のパネリストは,特許侵害が認められることを前提とする仮想事例について,自国法に基づき損害額の算定を行う上で問題となり得る点につきプレゼンテーションを行い,その後,参加者との間で意見交換が行われました。